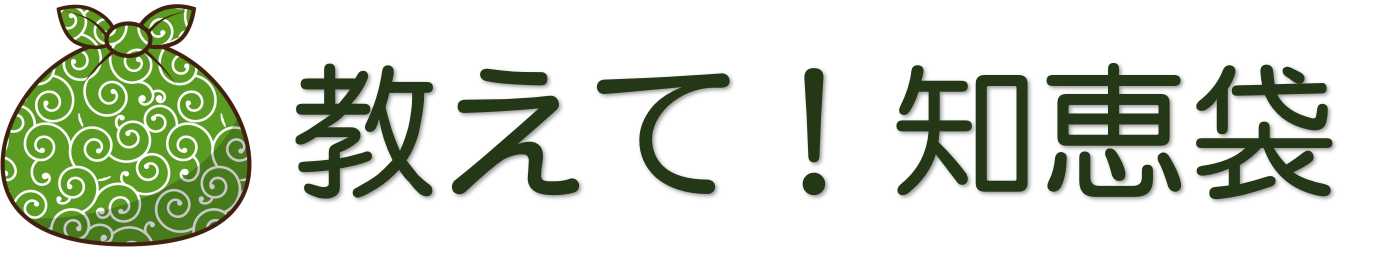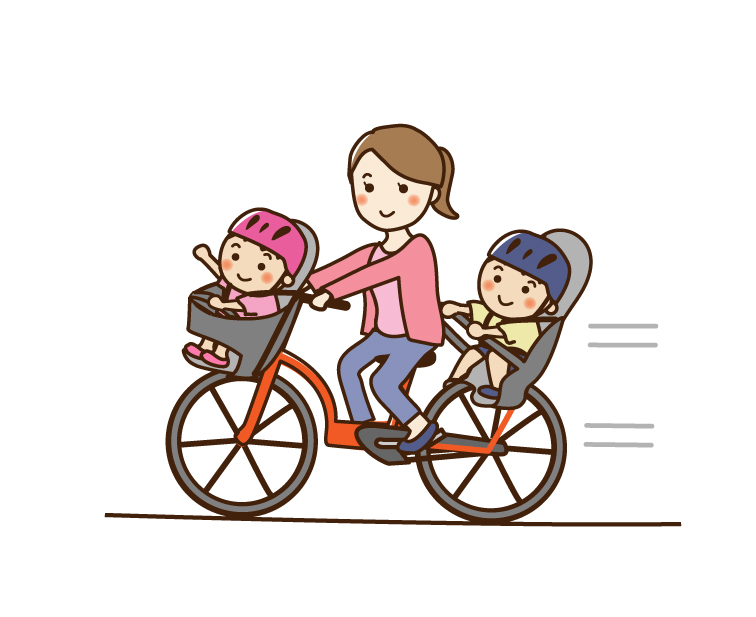ホトトギスは、万葉集や古今和歌集などの歌集に登場したりと、日本では古くから親しまわれ、多くの人にとって馴染み深い鳥。
しかし、ホトトギスの鳴き声は?というと、案外知られていなかったりします。
例えば、急に「ホトトギスの鳴き声は?」と聞かれたりすると、思わず「ホーホケキョ!」と答えてしまいそうではありませんか?。
そう、「ホーホケキョ」と鳴くのはホトトギスではなく、「春を告げる鳥」と呼ばれる「ウグイス」ですよね(苦笑)。
では、ホトトギスの鳴き声とは、いったいどんなものなのでしょうか?。
また、「ホーホケキョ」と鳴くウグイスと、ホトトギスの違いとは?。
今回は、ホトトギスとウグイスを比較しながら、「ホトトギスの鳴き声」については音声を交えるなど詳しくお伝えしていきます。
スポンサーリンク
ホトトギスとウグイスの違いとは?ホトトギスはウグイスの天敵?
「ホーホケキョ」って鳴くのは、ホトトギスのだっけ?ウグイスだっけ?と、何かと勘違いされてしまうホトトギスとウグイスですが、鳴き声はもちろん、生態や特徴など全く違う鳥です。
ところが、似ても似つかない鳥ではありながら、実はホトトギスはウグイス の天敵という驚きの関係性も浮かび上がってくるが興味深い点でもあります。
ホトトギスの生態や特徴は?
ホトトギスは「カッコウ目・カッコウ科」に分類される鳥で、その姿はカッコウに良く似ています。
大きさは全長約28センチほどあり、体の模様は、頭から背中は青灰色で、お腹の部分は黒色の横斑や黄色味がかったシマシマ柄が特徴的です。

また、ホトトギスは「夏鳥」として知られており、日本へは5月頃、夏よりも少し早めの時期に渡来してくるので、「夏を告げる鳥」といわれ、実際ホトトギスの鳴き声を聞くようになると、間もなく夏が来ることを実感する人もいるようです。
そして驚くことに、ホトトギスは自分の産んだ卵を自分で育てません。
他の鳥に育てさせるのです!。
その他の鳥というのが、なんと「ウグイス」なのです。
ホトトギスはウグイスが産んだ卵を取り除き、ウグイスの巣に自分の卵を産み付けて、自身では全く世話をせず、その巣の親であるウグイスにホトトギスの卵の世話をさせます。
つまり、ウグイスがホトトギスの育ての親ということになりますね。
このことを「托卵(たくらん)」といい、ホトトギスは卵を産んだらすぐに巣から飛び立ち、「後はすべてウグイスにお任せ」という、かなりの放任主義者なのです。
ホーホケキョの鳴き声を間違えらるだけでなく、自分が産んだ卵を排除され、卵の世話までさせられてしまう。
ウグイスにとってホトトギスは、まさに「天敵」に他ならないのです。
さらに不思議なことに、ウグイスに育てられ大人になって巣立ちを迎えたホトトギスは、またウグイスなど他の鳥の巣に托卵するようになるのです。
まさに「恩を仇で返す」というのはこのことを言うのかもしれませんが、ホトトギスの意外に知られていない、驚くべき生態であることが分かります。
ウグイスの生態や特徴は?
ウグイスは全長は約14センチほどとスズメと同じくらいの大きさで、ホトトギスに比べるとかなり小さく細身の鳥。見た目もスズメとよく似ています。
それもそのはず、ウグイスは「スズメ目ウグイス科ウグイス属」に分類される鳥。
頭から体はオリーブ褐色で、お腹の辺りの羽毛が白色をしているのが特徴的です。

ウグイスは別名「春を告げる鳥」とも呼ばれていて、春先から盛夏にかけてウグイスの鳴き声を聞くことが出来ます。
「日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)」の1つとされるお馴染みウグイスの「ホーホケキョ」ですが、実はオスのみの鳴き声で、繁殖期を迎えたオスが自分の縄張りにメスを呼んぶために発したり、ヒナ鳥のために餌を運ぶメスに、「縄張りに異常がない」ことを知らせるために発します。
「ホーホケキョ!」
なんと、1日に1000回以上も鳴くこともあるそうですよ!。
ウグイスのオスは「ホーホケキョ」の鳴き声の他にも、「ピピョピョピョピョ」と鳴き声も発します。
ウグイスのメスはというと、通常「チッチチッチ」と鳴きます。
スポンサーリンク
ホトトギスの鳴き声は?!
「ホーホケキョ」はウグイスの鳴き声。
では、ホトトギスの鳴き声とは、いったいどんなものなのでしょう?。
実際に、ホトトギスの鳴き声を音声で聞いてみましょう!。
いかがでしたか?。
ホトトギスの鳴き声は甲高く、ウグイスの鳴き声である「ホーホケキョ」とは全く似ても似つかないものでしたね。
また、ホトトギスの名前の由来は、「ホトホト」という鳴き声が聞こえたことから名付けられたという説がありますが、「ホトホト」と聞こえてきたでしょうか?。
さらにホトトギスの鳴き声は、「ホトホト」の他にも、江戸時代以降から様々な面白い表現がされてきたようです。
ホトトギスの鳴き声の表現の仕方
江戸時代以前までは、ホトトギスの鳴き声の表現は「ホトホト」のみだったのですが、江戸時代以降は色々と変化していき、色々な表現がされるようになりました。
その面白い表現というのが、
・タケヤブヤケタ(竹藪焼けた)
・ホンゾンカケタカ(本尊掛けたか)
・テッペンカケタカ(天辺欠けたか)
・トウキョウトッキョキョカキョク(東京特許許可局)
などといったものです。
先ほど紹介したホトトギスの鳴き声、皆さんはどれに近いものが聞こえてきましたか?。
ちなみに個人的には、「テッペンカケタカ」がホトトギスの鳴き声に近いのではないかと思いました。
「東京特許許可局」と聞こえるという意見も多いようですね。
みなさんは、いかがでしたか?。
まとめ
今回は、ホトトギスの鳴き声は?というところから、ついつい勘違いしてしまう「ホーホケキョ」と鳴くウグイスと、ホトトギスの生態や特徴について比較しながらお伝えしていきました。
ホトトギスとウグイスの違いは、
<ホトトギス>
・夏を告げる鳥
・体長は28センチで、カッコウと似ている。(ホトトギスはカッコウ科)
・ホトトギスの鳴き声は「ホトホト」や「トッキョキョカキョク」、「テッペンカケタカ」などの様々なユニークな表現がされている。
・ホトトギスは、「托卵」という他の巣に自分の卵を産み付けて面倒を見てもらうという行為を「ウグイス」にさせている。
<ウグイス>
・春を告げる鳥
・体長は14センチほどと、スズメくらいの大きさで、見た目もスズメと似ている。
・ウグイスの鳴き声「ホーホケキョ」はオスのみの鳴き声で、自分の縄張りにメスを呼ぶときや「縄張りに異常がない」ことを知らせるために発します。
「ホトトギス」と「ウグイス」は、鳴き声も生態も全く別のものでしたが、実は「天敵」という意外な関係性で結びついていいました。
ホトトギスがウグイスに「托卵」をしているので、ウグイスが生息する場所にホトトギスがいたり、ホトトギスが見られる時期が、ウグイスが見られる時期と同じになってしまったりするため、ホトトギスとウグイスを間違えてしまい、「ホーホケキョ」の鳴き声をも勘違いしてしまうのかもしれません。
ホトトギスの本当の鳴き声も、1度聞けば覚えてしまうほど特徴的なものではありませんでしたか?。
ぜひ、ホトトギスが渡来する季節になったら、耳をすませて、鳴き声を聞いてみていただけたらと思います!。
スポンサーリンク