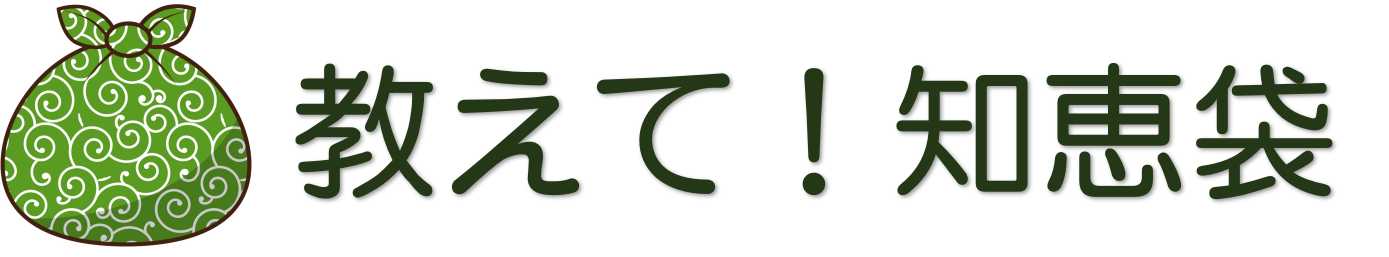もしや、あなたはお酒を飲まれましたね?(笑)。
それとも、これから?。
飲酒、つまりアルコールを飲むことじたいは、昔から「酒は百薬の長」といわれるように、適量であれば悪玉コレステロールの増加を抑え、善玉コレステロールが増えることから、心筋梗塞や狭心症を予防する効果が認めらているように、けして悪いことではありません。
いやいや、そんなコムズカシイことじゃなくて…
・飲酒後の車の運転は何時間後からできる?
・飲酒後にアルコールが抜ける時間は?
どれくらいが目安なのか、そのあたりが知りたい感じですよね。
まず、あなたがお酒飲んだ後なら「ちょっとだけなら大丈夫?」なんて絶対にダメですよ!。
それは、飲酒運転で捕まるだけではありません。
一歩間違えれば、取り返しのつかない悲劇につながります!。
逆に、あなたの大切なご家族が飲酒運転の事故に巻き込まれたら…。
おわかりですよね。
それでは、今すぐ知りたい「飲酒後の車の運転は何時間後からできる?」をメインに、飲酒運転で捕まったときの厳しい罰則や、飲酒後にアルコールが早く抜ける方法までを一気に紹介していきますから、しっかりついてきてくださいね!。
スポンサーリンク
飲酒後の車の運転は何時間後からできる?

その昔、「お酒を飲んでも2~3時間寝れば大丈夫だよ」なんて、お酒好きなオジサマたちが豪語していた時代もありました。
昨今も、前日の夜中までお酒を何杯も飲んでいたのに、「6~7時間寝れば飲酒運転にならない」と思っているのか、翌朝普通に車で通勤しているサラリーマンも多いといわれます。
実際問題、飲酒後の車の運転は何時間後からできるのでしょうか?。
飲酒後にアルコールが吸収・分解されるメカニズム
まずは、飲酒後にアルコールがカラダに吸収・分解されるまでのメカニズムを確認しておきましょう。
飲酒、つまりお酒を飲むと、そのアルコールは胃・小腸で吸収された後、血液へと溶け込み肝臓へ運ばれ分解がはじまります。
但し、アルコールの分解には時間がかかり、分解の順番待ちからあふれたアルコールは、血管を介して脳へと運ばれ麻痺させるようになります。
これが、お酒を飲んだ後に「酔う」メカニズム。
時間的には、飲み始めてから30分~1時間後にあらわれます。
酔った後の症状には個人差がありますが、過度な飲酒となれば酩酊状態となり千鳥足でフラフラしたり、最悪は意識を失い昏睡状態に陥ることもあります。
飲酒後は、時間とともにアルコールの分解が進み、徐々にアルコールは抜けていきますが、その時間は体重や体調、飲んだ量やアルコール度数の関係に加え、体質なども大きく影響します。
もしや、「飲酒後の車の運転は何時間後からできるのか?」を今すぐ知りたいところでしょうが、アルコールの分解に掛かる時間が大きく関係するものなので、ここでは一概にはいえません。
のちほど、飲んだお酒の種類と飲酒量から「目安」を計算してみましょうか。
スポンサーリンク
飲酒運転で捕まる!法律上の基準は?

「飲んだら乗るな!」
この言葉は、お酒を飲んで車を運転したら「飲酒運転で捕まる」からヤメテおけという意味ではありません!。
飲酒後の車の運転は、取り返しのつかない大事故につながりかねないからです。
そこを押さえた上で、「飲酒運転」の基準をあらためて確認していきましょう。
ところで、飲酒運転と呼ばれる交通違反にも、大きくわけて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類あるのはご存知ですか?。
さらに、お酒を飲んだ量(アルコール摂取量)と酔いの状態によって、違反の度合いや刑罰の判断が変わります。
酒気帯び運転は3つの基準にわけられ処分される!
酒気帯び運転とは、文字通りカラダにアルコールを帯びている(保有されている)状態で運転すること。
パトカーや警察官を道路に配置することで「検問所」を設置し、任意でアルコール検知器を用いて呼気に含まれるアルコール量を検査する形で、酒気帯び運転の撲滅に尽力しているのはご存知のとおり。
法律上、酒気帯び運転として捕まる基準は、
呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上
引用:警視庁|飲酒運転の罰則等
とあるように「呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg/l以上」が検出された場合、飲酒運転(酒気帯び運転)として捕まるわけですが、呼気検査で検出された数値によっては、3つ罰則・処分にわけられます。
酒気帯び運転で捕まる2つの基準と罰則・処分!
先のアルコール検知器で、呼気1L中に含まれるアルコール濃度が0.15mg以上となると「酒気帯び運転」の違反と判断され、計測された数値によって2つの罰則・処分にわかれます。
➀呼気1L中のアルコール濃度0.15mg~0.25mg
違反点数13点・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の上、免停期間は90日。
※前歴がある人は、即「免許取り消し」となります。
➁呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上
違反点数25点・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の上、免許取り消し。
※その後2年間、免許の再取得はできないと定められています。
基準値以下のアルコール濃度なら酒気帯び運転でも捕まらない!?
その一方、飲酒後でも呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば、アルコールが検知された以上、事実上の「酒気帯び運転」であっても違反とはなりません。
罰金や行政処分はありませんが、厳重注意を受けることは免れませんね。
しかし、飲酒運転で捕まる法律上の基準は、アルコール検知器で検出された呼気1L中に含まれるアルコール濃度だけではありません。
それこそが、「酒酔い運転」の基準です。
酒酔い運転の基準と罰則・処分!
飲酒運転の中で、もっとも重い罰則・処分が下されるのが「酒酔い運転」となりますが、その基準は呼気中のアルコール濃度がどれくらいかではなく、客観的に見て「正常な運転ができない」と判断されるか否かになります。
・直線上をまっすぐに歩けない
・質問への受け答えがあきらかにおかしい
などの情報から、警察官が「明らかにお酒で酔った状態」で「正常な運転ができない」と判断すれば、飲んだお酒の量に関わらず、たとえ呼気1L中のアルコール濃度が基準値以下となる僅かな量であっても「酒酔い運転」とみなされ捕まります。
そう、アルコールに弱い人は、ほんのちょっとの飲酒量でも酒酔い運転となってしまいかねません。
酒酔い運転の違反点数は35点・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の上免許取り消し。
※その後3年間は、免許の再取得はできないと定められています。
スポンサーリンク
飲酒後に車の運転ができるまでの時間の目安は?!

飲酒後に車の運転ができる時間は、飲んだお酒のアルコールがカラダの中で完全に分解された後。
本当の意味で「お酒が完全に抜けてから」となります。
アルコールが完全に分解されるまでの時間は、体重や体調、飲んだお酒の量・アルコール度数などが複合的に関係するので一概に言えませんが、一般的にいわれる「アルコールが抜けるまでの時間の計算式」によって、その目安を知ることができます。
体重60㎏~70㎏の男性を例にすると、1時間あたり分解・処理される「純アルコール量」は6g~7gとされています。
そうです、体重(kg) × 0.1 = 1時間あたり分解・処理される純アルコール量。
とはいえ、「よくわからない!」という人も多いはず。
1時間で分解・処理される、つまりアルコールが抜ける量をおよそお酒の種類毎に見てみると、
・生ビール中ジョッキ:1/4杯
・日本酒:約1/4合(約45ml)
・ウイスキー(ダブル):約1/4杯
どうですか?。
お酒好きな人からすれば「舐める」程の量ではありませんか?(苦笑)。
そう、カラダが1時間で分解・処理できるアルコール量って、かなり少ないものなんです。
飲酒後に車の運転ができるまでの時間の目安
いよいよ本題に入ってきましたね。
お酒の種類と体重別でみた車を運転できるまでの時間の目安!

飲酒後に車の運転ができるまでの時間の目安。
あくまで、使う計算式は「体重(kg) × 0.1 = 1時間あたり分解・処理される純アルコール量」を基本としますが、お酒の種類(度数)と体重別にわけて具体的にみていきましょう。
ビール・缶酎ハイ(5%)350mlの場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1缶 | 3.5時間 | 3時間 | 2.5時間 |
| 2缶 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
| 3缶 | 10.5時間 | 9時間 | 7.5時間 |
ストロング酎ハイ(9%)350mlの場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1缶 | 6.5時間 | 5時間 | 4.5時間 |
| 2缶 | 12.5時間 | 10.5時間 | 9時間 |
| 3缶 | 19時間 | 16時間 | 13.5時間 |
ハイボール(10%)350mlの場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1缶 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
| 2缶 | 14時間 | 12時間 | 10時間 |
| 3缶 | 21時間 | 18時間 | 15時間 |
日本酒(15%)1合(180ml)の場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1合 | 5.5時間 | 4.5時間 | 4時間 |
| 2合 | 11時間 | 9時間 | 8時間 |
| 3合 | 16時間 | 13.5時間 | 11.5時間 |
焼酎(25%)1合(180ml)の場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1合 | 9時間 | 7.5時間 | 6.5時間 |
| 2合 | 18時間 | 15時間 | 13時間 |
| 3合 | 27時間 | 22.5時間 | 19時間 |
ウイスキー(40%)ダブル(60ml)の場合
| 50kg | 60kg | 70kg | |
| 1杯 | 5時間 | 4時間 | 3.5時間 |
| 2杯 | 9.5時間 | 8時間 | 7時間 |
| 3杯 | 14.5時間 | 12時間 | 10時間 |
このように、飲んだお酒の種類やアルコール度数によって、飲酒後に車の運転ができるまでの時間の目安は大きく異なります。
単純に比較して、ビール350ml1缶と、流行りのストロング酎ハイ1缶とでは、およそ2倍の時間を要することがわかります。
どうでしょう。お酒を飲んだ後に車の運転ができるまでの時間は、これまでイメージしていたよりずっと長い時間ではありませんでしたか?。
アルコールの分解には、それだけ多くの時間がかかるものなんです。
「飲酒後に車の運転ができるまでの時間は?」と考えること自体が、ナンセンスなことだと思えてきませんか?。
スポンサーリンク
飲酒後にアルコールが早く抜ける方法とは?

お酒を飲んだなら…。
飲酒運転で捕まるのも嫌ですし、もちろん飲酒が原因の事故などあってはなりません。
暑い夏の晩、チョッと冷えたビールで喉を潤そうと缶ビール1本飲んだだけでも、先の目安を参考にすれば、およそ3時間は車の運転はできないことになります。
もしやあなたが知りたいのは、「どうしたら早くアルコールが抜けるのか?」でしょうか?。
たくさん水を飲んだところで、体内のアルコール濃度は下がったとしてもアルコールそのものはカラダに留まったままです。
実際には、飲んだ直後に嘔吐するなど、アルコールがカラダに吸収される前に排出するしかないといわれます。
巷では、サウナや運動することで汗をかくと早く抜けるとか、とにかく寝れば抜けるなどの噂が絶えませんが、いったい本当にアルコールが早く抜ける方法はあるのでしょうか?。
サウナで汗をかくとアルコールが早く抜ける?
そもそも論ですが… お酒を飲んだ後にサウナを利用するのはかなりの危険行為です(苦笑)。
アルコールを早く抜くためのサウナは、絶対にやめましょう!。
なぜなら、お酒を飲んだ直後のカラダは利尿作用によって脱水状態であることが多く、その状態でサウナへ入れば…。
そう、カラダの水分がさらに抜けることで、ますます脱水症状が悪化してしまいます。
「二日酔いにはサウナ!」
なんていう人もいますが、それも逆効果!。
サウナの効能で血行が急激に高まると、お酒を飲んだときに発生し、二日酔いの原因ともされる「アセトアルデヒド」が急速にカラダ中に回ることで、二日酔いの症状が悪化するだけでなく、酩酊状態になってしまう人もいるほどです。
最悪は、命に危険を及ぼします。
運動して汗をかけばアルコールが早く抜ける?
アルコールを早く抜くには、運動して汗をかけばいいと思っている人も多い…。
しかし、運動で汗をかくことも「サウナで汗をかく」のと同じ理由で、アルコールが早く抜ける効果が期待できない上に、命に危険を及ぼしかねません。
つまり、アルコールを発汗によってカラダから排出させようとする考え方は、ハッキリ言って間違いです。
飲む前にサプリ・ドリンク剤を飲む効果は?
・ヘパリーゼ
・ウコンのチカラ
・液キャベ コーワV
など、二日酔い防止や二日酔いからの回復が早いなどの効果が人気のサプリやドリンク剤。
「飲んだ翌朝も辛くない」「二日酔いが軽くなる」などの声も多く、お酒好きのユーザーから絶大な信頼を得ています。
肝臓が健康な状態であれば、ウコンやコウジンなど生薬の効能でアルコールを分解が促されるのかもしれませんが、車を運転できるまでの時間を早める程の効果はありません。
サプリやドリンク剤に期待できるのは、あくまで「二日酔い防止」程度に留めておきましょう。
寝ればアルコールが抜けるは大きな間違い!

お酒を飲んでしまったら、アルコールが抜けるまで車内でひと眠りしてからハンドルを握る。
ひと昔前では、よく見られた光景かもしれませんね。
しかし、「寝ればアルコールが抜ける」には大きな間違いが潜んでいます。
睡眠中は、頭神経が休むでけでなく、カラダの機能をも睡眠した状態へ。
つまり、寝ることによって、逆に肝臓のアルコール分解機能を低下させてしまうということ。
例えば、お酒を飲んで4時間寝た人に比べて、寝ずに起きていた人の方が約2倍もアルコールの分解が進んでいたという研究結果があるほどです。
「寝ればアルコールが抜ける」
というのは大間違い。
先に紹介したように、体重60㎏の人が日本酒1合やストロング酎ハイ350mlを飲んだ後、アルコールが抜けるまでの時間の目安は5時間ほどですが、飲んだ後にすぐに寝てしまうとかえって時間がかかることになるのです。
・サウナで汗をかく
・運動で汗をかく
・飲む前にサプリ・ドリンク剤を飲む
・寝る
これらは、アルコールを早く抜く方法としてよく聞く方法ですが、どれも決してお酒を飲んだ後に早く車が運転できる方法ではないようですね。
試しに、手軽な価格の「アルコールチェッカー」を常備しておいて、本当に運転できる状態なのか?を確かめてみるのもいいかもしれませんね。
一応、念のためにというコトで(苦笑)。
まとめ
今回の「飲酒後の運転!何時間後からできる?アルコールが抜ける時間の目安は?」を、最後まで読んでいただきありがとうございます。
お酒を飲んだ後に車を運転すること自体、ナンセンスな考えだったと思ってもらえましたか?。
お酒を飲んだ後に、どれだけ早く運転できるのかを助長する記事にしたくなかったものですから…(苦笑)。
あらためて、お酒を飲んだ後にアルコールが抜けるまでの時間は、意外と長い時間かかるモノなんですね。
チョッと一杯のつもりで生ビール2杯も飲んだのなら、間違いなく翌朝まで車の運転はできません。
深夜まで飲んでいたなら、翌日は丸々1日運転することは控えた方がいいくらいです。
タクシーや運送業界では、業務24時間前からの飲酒を禁止している企業も多いのも、ご尤もな規則だと思います。
飲酒運転で捕まる「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」の基準についても紹介しましたが、怖いのは捕まることではありません!。
飲酒による判断能力が低下した状態での車の運転は、一歩間違えれば、取り返しのつかない悲劇につながります!。
「飲んだら乗るな」
肝に銘じましょう。わたしも気をつけます(苦笑)。
そうそう、よく飲み会に自転車で向かわれる方も見掛けますが、自転車だって飲酒運転の対象ですからね。
スポンサーリンク