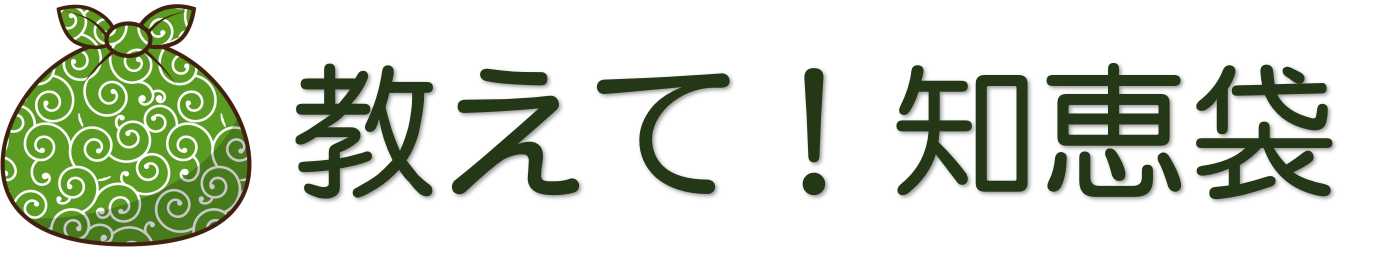「師走」という言葉を聞くと、なんだかソワソワしてきませんか?。
「もうすぐお正月」という感じが高まってきますよね。
ところで、師走とは暦の上で「12月」を意味しますが、「どうして師走っていうの?」と子供たちに聞かれることがあります。
何気ない子供の質問ですが、「先生が走るから」と答えても子供たちの反応はイマイチ。
どうしたら子供たちに師走の意味をわかりやすく伝えられるのでしょう。
そこで、今回は「師走の意味!子供向けに簡単に説明をするなら?」と題してまとめてみました。
スポンサーリンク
師走の意味は?
現在日本で採用されている新暦(陽暦)では、1年12ヶ月を1月~12月と数字で表されていますが、旧暦(陰暦)が採用されていた明治以前は、それぞれの月を季節感が伝わる「和風月名」で表現されていました。

師走とは元々、旧暦の1年最後の月を指していた月名ですが、新暦が採用された明治以降も12月を師走と呼ばれるようになったのです。
しかし、新暦の12月を指す師走も、旧暦の最後の月(12月)とは実際の季節感が異なります。
旧暦(陰暦)と新暦(陽暦)には1ヶ月ほどのズレがあり、旧暦の最後の月(12月)は現在の新暦での12月下旬~翌年2月上旬頃に当たるといいます。
それこそ、1年で最も寒さが厳しい時期ですね。
スポンサーリンク
師走の語源は?
それでは、12月を表す「師走」という言葉の語源はどこにあるのでしょう。
ここでは、代表的な4つの説を見ていきましょう。
・僧侶(お坊さん)という説
・神職(御師)という説
・古い書物からという説
・やるべき事はやり遂げる説
師走の師はお坊さん僧侶(お坊さん)が走り回るという説

師走の語源としてよく知られているのが、師走の師は僧侶(お坊さん)という説でしょう。
昔の日本では、年末になると多くの家庭で、ご先祖様の供養で仏事を行う習慣がありました。
その時に欠かせないのが「僧侶(お坊さん)」です。
あちらこちらの家庭に呼ばれお経を唱えるために、忙しく走り回っている僧侶の姿がありました。
僧侶は「師」を指していましたので、「師が馳せる(走る)」という言葉から「師走」になったという説です。
また、現代の子供たちは「師」というと、およそ「先生」をイメージすると思います。
たしかに昔は、お坊さんが子供たちに勉強を教えていた時代もありました。
そこから、「先生(師)が忙しく振舞う(走り回る)月」という説もあるようです。
御師(神職)が忙しく走る説

「師」は僧侶(お坊さん)だけでなく、御師と呼ばれる社寺に所属し、参拝者を案内する他、参拝や宿泊などの世話をされる方をも指します。
参拝者が増える年末になると、御師が案内やお世話に忙しくなることから「師が走る=師走」となったという説です。
古い書物の記述「シハス」が師走になった説
万葉集や日本書紀といった古い日本の書物の中に、「十二月(シハス)や「十有二月(シハス)」という記述があります。
少なくとも奈良時代には、「十二月」を「シハス」と読んでいたことがわかります。
その後、漢字の「師走」を当て字にして表したという説です。
曖昧な感じも否めませんが、これも1つの説になっています。
1年の最後にやるべき事はやり遂げるという説
12月は、もちろん1年を締めくくる最後の月です。
やるべき事は全てやり遂げる月ということに、「為果つ(しはつ)」という言葉があります。
・仕事をやり遂げる
・勉強をやり遂げる
どうやら、1年の最後しっかりやり遂げる月「師走」は、師でなく自分が頑張らなきゃならない月のようですね。
スポンサーリンク
師走の意味を子供たちに簡単に説明するなら?
今回の記事のメインテーマとなりますが、師走の意味を子供たちに簡単に説明するなら、どうしたらわかりやすく、理解が深まるのでしょうか。
ここでは、小学生の場合と、それ以下(未就学児)の年齢の場合に分けて考えてみました。
小学生の場合
小学校は、意外と12月に学校行事が多いところがあります。
小学生のお子さんに「師走」を簡単に説明するなら、
12月は色々な学校行事があるよね。みんなはそれに向かって頑張ってるでしょ。先生もそれに向かって一生懸命頑張ってるよね。
師走は「先生が走る」と書くように、この様子を感じに表したものなんだよ。
なんて如何でしょうか。
その上で、先に紹介した師走の語源となる4つの説などを交えて説明すると、イメージが湧きやすいかもしれませんね。
幼稚園・保育園など小さな子供の場合
幼稚園や保育園に通う未就学児の小さなお子さんの場合、当然ながら「師走」の意味や由来などは、まだ難しくて理解できないでしょう。
12月の幼稚園や保育園の先生の忙しさや、クリスマスを例に説明されては如何でしょうか。
師走の「師」は、幼稚園や保育園とかの先生をいうんだよ。
12月は1年の最後の月でしょう。だから最後の月にまとめのお仕事、やり残したお仕事を片付けるために先生たちは忙しく走り回ってるの。
1年の最後で一番忙しい月なんだね。
だから、先生が走り回る12月は師走って呼ばれているんだよ。
また、クリスマスのサンタさんを「師」に例えることもできますね。
世界中の子供たちへのプレゼントの準備や、クリスマス当日に配って回るのに、サンタさんは12月は大忙しで走り回らなきゃだよね。
サンタさんは、世界中の寝ている子供たちにプレゼントを配りながら、そっと「いい子になってね」と声を掛けるんだって。
サンタさんも世界中の子供たちのいい先生になるのかな…
となれば、サンタ先生が走り回るから「師走」。ちょっと厳しいこじつけかな…。
スポンサーリンク
師走の意味にちなんだ昔ばなし「四十八豆と大黒天」
昔、与作という怠け者の若者がいました。
両親を亡くしたのち、おばさんの世話になりながら毎日ぶらぶらと暮らしていましたが、通り掛かった婚礼の行列を見た与作は「いつかお金を貯めて嫁をもらいたい」と考えます。
与作は家の神棚の大黒天様に「楽してお金が貯まるように」とお祈りしました。
すると、夢に大黒天様が現れ「四十八種類の豆を作って、師走十二月の九の夜に炒った豆を供えなさい。さすれば一生、楽に暮らせるだろう」とのお告げを得られたのです。
与作はあちこちの家から豆をもらってきては植え大切に育て、少しづつ豆の種類を増やしていきましたが、集めた豆は四十六種類だけ。どうしても四十八種類を集めることが出来ませんでした。
ところがある夜、夢の中に再び大黒天様が現れて
「残りの二つは手足にできたマメのこと。今まで頑張てきたように、しっかり汗水流して働きなさい。
そうすれば、今後の暮らしも楽になであろう」と言いました。
その言葉を聞いた与作は、大黒天様の言うことを聞いて、しっかり働くことで暮らしが良くなり、お嫁さんをもらい暮らしたといわれます。
まとめ
コロナ禍の今、なかなか外出がままならない方も多いと思います。
家にいる時間が長くなっている今こそ、お家でお子さんといろいろな言葉のお話をするのも楽しいのではないでしょうか。
今回の「師走」の意味だけでもたくさんありますね。
それに合わせて、今回紹介した「四十八豆と大黒天」のような師走にちなんだ「日本の昔話」を話して聞かせると、子供たちの心の世界が広がるのではないでしょうか。
スポンサーリンク