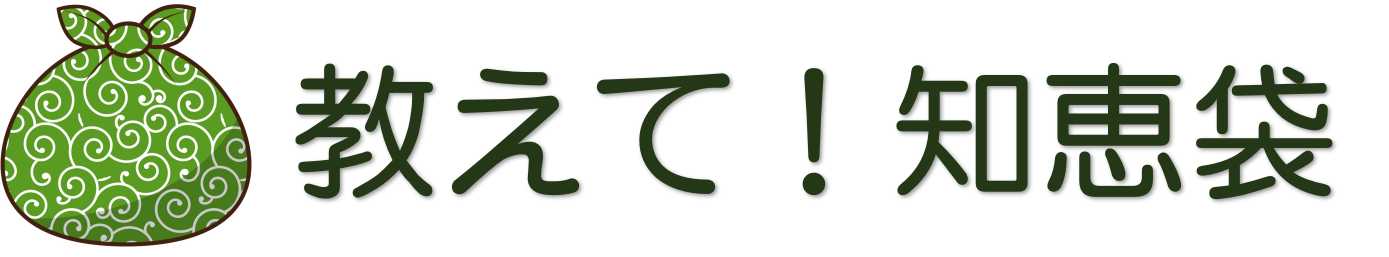日本の春を象徴する桜。
待ち焦がれていたお花見の計画を立てる方も多いのではないでしょうか?
「桜の見頃はいつ?」「開花から散るまでどれくらい?」といった疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。
この記事では、桜の開花から満開、そして散り際までの期間を詳しく解説し、見頃を逃さず、桜を最大限に楽しむための情報をお届けします。
スポンサーリンク
桜の開花から散るまでの期間
春の訪れを告げる桜。その美しい姿を長く楽しみたいと思うのは、誰もが同じ気持ちですよね。
でも、桜の開花から散るまでの期間って、意外と短いんです。
ここでは、桜の開花、満開、散り始めの定義と、それぞれの期間について詳しく解説していきます。
桜の開花、満開、散り始めの定義
桜の開花、満開、散り始めとは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
桜の開花とは

気象庁の定義によると、標本木で5~6輪以上の花が開いた状態を「開花」といいます。
桜の標本木とは?

桜が開花する時期に注目されるのが「標本木」です。
気象庁が桜の開花宣言を行うために観測する特別な桜の木で、全国各地にあり、全部で58本あります。
例えば、東京は靖国神社(千代田区)の境内に、京都は二条城(京都市中京区)に、大阪は大阪城公園(大阪市中央区)にあります。
靖国神社のソメイヨシノは1966年から54年間も「標本木」を務めているのです。
都道府県ごとに「標本木」がありますが、沖縄や北海道などのように広いところや離れ島があるところは「標本木」が各地にあります。
樹種は原則として「ソメイヨシノ」ですが、沖縄県(石垣島、宮古島、那覇、南大東島)は「カンヒザクラ」、北海道(稚内、旭川、網走、帯広、釧路)は「エゾヤマザクラ」です。
お住まいの地域の標本木について詳しくはこちら → 桜の開花を決める標本木について 桜.jp
桜の満開とは
標本木で約80%以上のつぼみが開き、花で覆われた状態を「満開」といいます。
一面が桜色に染まる、まさに絶景の瞬間です。
桜の散り始めとは
満開を過ぎ、花びらが散り始めた状態を「散り始め」といいます。儚くも美しい、桜の最後の姿を見ることができます。
・桜の満開: 標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態
・桜の散り始め: 満開を過ぎ、花びらが散り始めた状態
桜の開花から散るまでの期間と日数

では、一般的な桜の開花から散るまでの期間はどれくらいなのでしょうか?
桜の開花から満開まで
一般的には、開花から満開までは1週間ほどといわれています。
ただし、これはあくまで目安であり、気温や天候によって変動します。
桜の満開から散り始めまで
満開から散り始めまでも、1週間ほどといわれています。
つまり、満開の時期を逃すと、あっという間に桜は散ってしまうのです。
・満開から散り始めまで: 約1週間
桜の見頃を最大限に楽しむための基礎知識
桜の見頃を最大限に楽しむためには、開花時期を左右する要素や、桜の種類ごとの特徴を知っておくことが大切です。
ここでは、桜の開花を左右する要素と、代表的な桜の種類について解説します。
桜の開花を左右する要素
桜の開花時期は、主に以下の要素によって左右されます。
気温
桜の開花は、気温の上昇とともに進みます。
冬の間に一定期間低温にさらされることで、花芽が休眠から目覚め、春の気温上昇とともに成長を始めるのです。
そのため、気温が高い年は開花が早まり、低い年は遅れる傾向があります。
特に、開花直前の気温は、開花を大きく左右する要因となります。
気温が高い日が続くと、開花が一気に進み、あっという間に満開を迎えることもあります。
逆に、開花直前に寒の戻りがあると、開花が遅れることがあります。
日照時間
日照時間も、桜の開花に影響を与えます。
日照時間が長いと、桜の成長が促進され、開花が早まることがあります。
特に、開花直前の日照時間は、開花を大きく左右する要因となります。
日照時間が短いと、桜の成長が遅れ、開花が遅れることがあります。
また、日照時間が不足すると、花芽が十分に成長せず、開花しないこともあります。
降水量
降水量も、桜の開花に影響を与える要素の一つです。
適度な降水量は、桜の成長に必要な水分を供給しますが、開花時期に雨が多いと、花びらが早く散ってしまうことがあります。
特に、満開時に雨が降ると、花びらが一気に散ってしまい、見頃が短くなることがあります。
また、強風を伴う雨の場合は、さらに花びらが散りやすくなります。
地域の特性
同じ日本国内でも、地域によって気候が大きく異なるため、桜の開花時期も大きく異なります。
一般的に、南に行くほど開花が早く、北に行くほど遅くなる傾向があります。
また、同じ地域でも、標高や海岸からの距離によって開花時期が異なることがあります。
例えば、都市部ではヒートアイランド現象の影響で、周辺地域よりも開花が早まることがあります。
また、山間部では標高が高いほど気温が低いため、開花が遅れることがあります。
・日照時間: 長いと開花が早まる
・降水量: 適度な降水量は必要だが、多すぎると花が早く散る
・地域の特性: 南に行くほど開花が早く、北に行くほど遅れる
・これらの情報を参考に、お花見の計画を立ててみましょう。
スポンサーリンク
桜の種類と見頃
日本には、ソメイヨシノをはじめ、さまざまな種類の桜があります。
種類によって開花時期や特徴が異なるため、それぞれの桜に合った時期に見頃を迎えることができます。
桜の代表的な品種と特徴
ソメイヨシノ(染井吉野):

- 日本で最も一般的な桜で、淡いピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は3月下旬から4月上旬頃で、満開になると一面が桜色に染まります。
ヤマザクラ(山桜):

- 日本に自生する野生種の桜で、ソメイヨシノよりも濃いピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は4月上旬から中旬頃で、山間部で見ることができます。
シダレザクラ(枝垂桜):

- 枝が垂れ下がるように咲く桜で、ピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は3月下旬から4月上旬頃で、優雅な姿が人気です。
ヤエザクラ(八重桜):

- 花びらが幾重にも重なって咲く桜で、ピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は4月中旬から下旬頃で、ボリュームのある花が楽しめます。
カンヒザクラ(寒緋桜):

- 沖縄などで見られる早咲きの桜で、濃いピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は1月下旬から2月上旬頃で、寒い時期に春の訪れを感じさせてくれます。
カワヅザクラ(河津桜):

- 静岡県の河津町で発見された早咲きの桜で、ピンク色の花が特徴です。
- 開花時期は2月下旬から3月中旬頃で、開花期間が長く、約1か月ほど花を楽しむことができます。
品種ごとの開花時期
桜の種類によって開花時期が異なるため、早咲きから遅咲きまで、さまざまな桜を楽しむことができます。
早咲きの桜としては、1月下旬から咲き始めるカンヒザクラや、2月下旬から咲き始めるカワヅザクラなどがあります。
遅咲きの桜としては、4月下旬から咲き始める八重桜などがあります。
長く楽しめる桜の品種
桜の種類によっては、比較的長く花を楽しむことができる品種もあります。
例えば、カワヅザクラは開花期間が長く、約1か月ほど花を楽しむことができます。
また、八重桜は花びらが散りにくいため、比較的長く花を楽しむことができます。
・ヤマザクラ: 4月上旬~中旬
・シダレザクラ: 3月下旬~4月上旬
・八重桜: 4月中旬~下旬
・カワヅザクラ: 2月下旬~3月中旬
これらの情報を参考に、お花見の計画を立ててみましょう。
スポンサーリンク
全国の桜の名所と最新開花情報
せっかくお花見に行くなら、桜の名所で満開の桜を見たいですよね。
ここでは、全国の主要な桜の名所と、最新の開花情報をチェックする方法について解説します。
主要な桜の名所の紹介
日本全国には、息をのむほど美しい桜の名所がたくさんあります。
ここでは、特におすすめのスポットをいくつかご紹介します。
上野恩賜公園(東京都):

- 都内屈指の桜の名所で、約1200本の桜が咲き誇ります。
- 公園内には、博物館や動物園などもあり、一日中楽しめます。
吉野山(奈良県):

- 約3万本のシロヤマザクラが山全体を覆い、圧巻の景色が広がります。
- 標高によって開花時期が異なるため、長い期間桜を楽しめます。
弘前公園(青森県):

- 約2600本のソメイヨシノが咲き誇り、お堀に映る桜が美しいスポットです。
- 夜はライトアップされ、幻想的な雰囲気を楽しめます。
姫路城(兵庫県):

- 世界遺産の姫路城と桜のコントラストが美しい、人気の観光スポットです。
- 約1000本のソメイヨシノが咲き誇り、お城を囲むように桜が咲きます。
これらの他にも、全国各地に魅力的な桜の名所があります。ぜひ、お近くの桜の名所を探して、お花見に出かけてみてください。
最新の桜の開花情報をチェックする方法
桜の開花時期は、気温や天候によって変動するため、最新の情報をチェックすることが大切です。
- 気象庁では、全国の桜の開花予想や開花状況をリアルタイムで公開しています。
- 各都道府県の気象台のウェブサイトでも、詳細な情報を確認できます。
- ウェザーニュースでは、全国の桜の開花予想や開花状況を、地図や写真を使って分かりやすく公開しています。
- お花見スポットの情報も充実しており、役立つ情報が満載です。
桜.jp:
- 桜に関する様々な情報を提供しているサイトです。
- 全国の桜の名所や開花情報を、都道府県別に確認できます。
各都道府県、自治体のホームページ:
- 各都道府県や、各自治体のホームページでも、桜の開花情報やイベント情報が掲載されていることがあります。
これらのサイトや情報を活用して、お花見の計画を立ててみましょう。
・お花見スポットの情報もチェックして、計画を立てる。
・各都道府県や自治体のホームページも確認すると、より詳しい情報を得られる。
これらの情報を参考に、ぜひ、お近くの桜の名所を探して、最新の開花情報をチェックして、お花見に出かけてみてください。
スポンサーリンク
お花見を120%楽しむための準備とコツ

せっかくお花見に行くなら、準備万端で、心ゆくまで楽しみたいですよね。
ここでは、お花見を120%楽しむための準備とコツについて解説します。
持ち物と服装
お花見を快適に楽しむためには、持ち物と服装が重要です。
持ち物
- レジャーシート:人数に合わせた大きさのものを用意しましょう。
- お弁当や飲み物:手作りでも購入でもOK。温かい飲み物もあると嬉しいですね。
- ウェットティッシュやゴミ袋:あると何かと便利です。
- 防寒具:昼間は暖かくても、夕方から夜は冷えることがあるので、上着やひざ掛けなどを持参しましょう。
- カメラやスマートフォン:美しい桜の写真を撮りましょう。
- モバイルバッテリー:スマートフォンで写真をたくさん撮るなら必須です。
- 懐中電灯(夜桜の場合):足元を照らすのに役立ちます。
服装
- 動きやすい服装:長時間座っていても疲れない服装を選びましょう。
- 温度調節しやすい服装:脱ぎ着できる上着があると便利です。
- 歩きやすい靴:公園内を歩き回ることを考慮して、歩きやすい靴を選びましょう。
マナーと注意点
お花見は、みんなで楽しむイベントです。マナーを守って、気持ちよく過ごしましょう。
場所取りについて
- 必要以上に広い場所を確保しないようにしましょう。
- 後から来る人のために、場所を譲り合いましょう。
公園によっては、場所取りが禁止されている場合があるので、事前に確認しましょう。
ゴミについて

- ゴミは必ず持ち帰りましょう。
- 公園にゴミ箱がある場合は、分別して捨てましょう。
騒音について
-
- 大声で騒いだり、音楽を大音量で流したりするのは控えましょう。
- 周りの人に配慮して、静かに楽しみましょう。
その他
- 桜の木を傷つけたり、枝を折ったりするのはやめましょう。
- 火気厳禁の場所では、火を使わないようにしましょう。
- 公園のルールを守って、楽しく過ごしましょう。
桜を長く楽しむコツ
桜を少しでも長く楽しむためのコツを紹介します。
早咲き・遅咲きの桜を選ぶ
早咲きのカンヒザクラやカワヅザクラ、遅咲きの八重桜などを選ぶことで、長い期間桜を楽しめます。
複数の場所を訪れる
標高や場所によって開花時期が異なるため、複数の場所を訪れることで、長い期間桜を楽しめます。
桜の開花情報をこまめにチェックする
気象庁のウェブサイトやウェザーニュースなどのサイトで、最新の開花情報をチェックしましょう。
散り際の桜も楽しむ
花吹雪や散った花びらが絨毯のように広がる景色も、また違った美しさがあります。
・マナーを守って、みんなで気持ちよくお花見を楽しみましょう。
・桜の種類や場所を選ぶことで、長く桜を楽しめます。
これらの情報を参考に、お花見を120%楽しんでください。
まとめ
日本の春を彩る桜。その開花を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、桜の開花から散るまでの期間、見頃を最大限に楽しむための基礎知識、そしてお花見を120%楽しむための準備とコツについて解説しました。
桜の開花から満開、そして散り際までの期間は、気温や天候によって大きく左右されます。
だからこそ、最新の開花情報をこまめにチェックすることが大切です。
気象庁やウェザーニュースなどの信頼できる情報源を活用して、お住まいの地域の開花状況を把握しましょう。
また、桜の種類によって開花時期や特徴が異なることを知っておくと、より長く桜を楽しむことができます。
早咲きのカンヒザクラやカワヅザクラ、遅咲きの八重桜などを選んだり、複数の場所を訪れたりすることで、さまざまな桜の表情に出会えるでしょう。
お花見は、準備とマナーを守ってこそ、みんなで気持ちよく楽しめるイベントです。
持ち物や服装をしっかり準備し、場所取りやゴミ、騒音など、周りの人への配慮も忘れずに。
桜の木を傷つけたり、枝を折ったりしないよう、自然への敬意も払いましょう。
そして、桜を最大限に楽しむためには、散り際の桜にも目を向けてみてください。
花吹雪や、散った花びらが絨毯のように広がる景色は、満開の桜とはまた違った美しさがあります。
今年の春は、この記事で得た知識を活かして、計画的に桜を楽しんでみませんか?
満開の桜の下で、素敵な思い出を作ってください。
スポンサーリンク