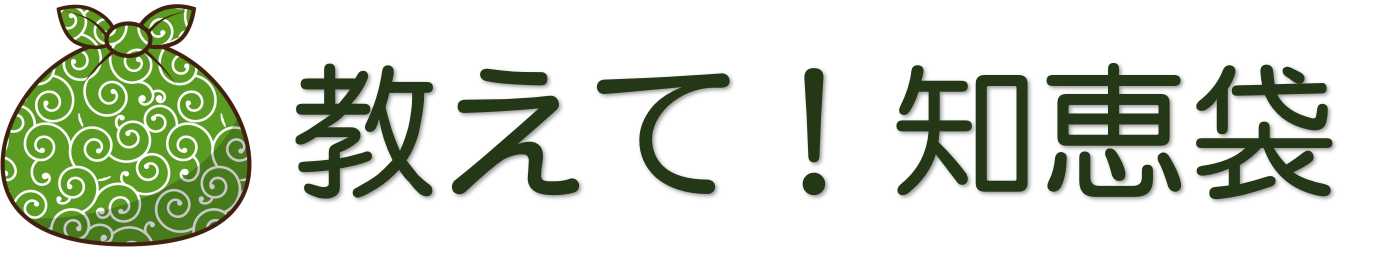梅雨から夏にかけて、雨上がりにカタツムリを見つけることはありませんか?。
子供たちは「カタツムリを飼いた~い!」なんて無邪気に捕まえてくるかもしれませんね。
けれど、意外と知らないカタツムリの生態や飼い方。
今回は、カタツムリの餌となる葉っぱや野菜、飼い方、注意点などを詳しく探っていきます。
夏休みの自由研究のテーマにも使える内容なので、親子で一緒にカタツムリについて学んでいきましょう!
スポンサーリンク
日本に生息するカタツムリの種類
日本にはおよそ800種類ものカタツムリが生息しています。
その中でも、私たちが目にしやすい代表的な種類をいくつか見ていきましょう。
カタツムリの種類を見分けるポイントは「殻」です。
・巻き方
・形
・色
・模様(すじの入り方)

オナジマイマイ

オナジマイマイは日本で最も目にするカタツムリで、北海道南部以南と、本州・四国・九州など広く各地に生息しています。
殻は半透明の黄白色から茶褐色で、褐色の帯が1本入るものと入らないものがあります。
大人の殻の大きさは約2cmほど、やや小型のカタツムリです。
ヒダリマキマイマイ

出典:Wikipedia|ヒダリマキマイマイ|著者:アンガス・デイヴィソンと千葉S
ヒダリマキマイマイは、本州の中部地方・関東地方・東北地方に生息し、伊豆諸島や石川県舳倉島・山形県飛島など周辺離島にも生息しています。
その名のとおり左巻きの殻が最大の特徴で、大人の殻の大きさは5㎝ほどになる大型のカタツムリです。
ミスジマイマイ

ミスジマイマイは、本州の関東地方南西部や中部地方南東部のほか、伊豆諸島の神津島以北に生息しています。
名前のとおり、殻に3本の褐色の目立つ帯が入ることが多いのが特徴で、大人の殻の大きさは3㎝ほどです。
コベソマイマイ
コベソマイマイは、本州では関東地方西部以西、多くは四国・九州のほか、隠岐諸島や五島列島などの周辺諸島、薩南諸島の口永良部島などに生息しています。
殻に細かい赤褐色のスジが入り、巻きの数は最大で6層を超えます。
大人の殻の大きさは5㎝ほどになる大型のカタツムリです。
ウスカワマイマイ
ウスカワマイマイは、北海道南部から九州までと、日本産のカタツムリの中ではオナジマイマイに匹敵するほど幅広い地域に生息しています。
名前のとおり、殻は薄く半透明で、殻を透かして体の斑点が見えることがあるほど。
大人の殻の大きさは、約2.5㎝ほどの小型のカタツムリです。
スポンサーリンク
カタツムリの餌は何?葉っぱの種類は?野菜も食べる?

カタツムリは、葉物野菜などの野菜類の他、果物など植物性のものを広く好んで食べます。
カタツムリが食べる野菜類は?
カタツムリが好んで食べる葉物野菜は、
・キャベツ
・白菜
・レタス
・ほうれん草
・チンゲン菜
その他、私たちの身近な食材となる野菜の中でも水分に多いものを好んで食べ、真っ赤なトマトも食べるようです。
・きゅうり
・ニンジン
・トマト
・カボチャ
・パプリカ
ちなみに、りんごやバナナ、桃など果物類もよく食べますよ。
カタツムリが好んで食べる果物類
・りんご
・バナナ
・スイカ
・桃
・イチゴ
カタツムリも1匹1匹好き嫌いが異なります。
いろいろな種類の野菜や果物を試しに与えながら好みを探ってみましょう。
カタツムリはアジサイの葉っぱは食べない

梅雨といえばアジサイ、アジサイといえばカタツムリという感じに多くの方はイメージすると思います。
しかし、アジサイの葉っぱには毒があることをカタツムリは知っているので、カタツムリはアジサイの葉っぱを食べることはありません。
カタツムリは、外敵から身を守るため、雨や風防止のためにアジサイの葉っぱや枝、茎を利用しているといわれています。
スポンサーリンク
カタツムリは卵の殻やコンクリートも食べる
カタツムリは殻を背負って生まれ、殻と共に大人へと成長していきます。
>カタツムリは殻も一緒に成長する?!殻の形や年輪が成長の証し!<
その殻を大きく頑丈なものへ成長させるため、カタツムリは野菜や果物だけでなくカルシウムを含む餌も求めます。
自然界で生きるカタツムリも、住宅のブロック塀などコンクリートを食べることで効率よくカルシウムを摂取しているようです。
カタツムリはカルシウム不足に陥ると、仲間が背負う殻を食べる「共喰い」をはじめてしまいます。
カルシウムもしっかり摂れるよう、カタツムリの餌には、卵の殻やアサリなどの貝殻、入手できればコンクリートの破片なども与えるのがポイントです。
カタツムリには歯がある

カタツムリは「歯舌(しぜつ)」と呼ばれるヤスリ状の歯を持ち、その数は1万本以上にもなるといわれています。
カタツムリは夜行性で基本的に夜になると活発に活動しはじめますが、静かな部屋でカタツムリを飼育していると、餌の表面を削り取りながら食べる音が聞こえることがあります。
そんな頑丈な歯があるからこそ、卵の殻や貝殻、コンクリートまでガシガシ食べられるのですね。
スポンサーリンク
カタツムリの飼い方
カタツムリを飼うにあたっての餌の疑問がクリアしたところで、ここからはカタツムリの飼い方を確認していきます。
カタツムリを飼うには、以下のものが必要です。
・霧吹き
・土
・木の枝(流木)
・餌(野菜・卵の殻など)
昆虫飼育ケース
カタツムリはツルツルした壁面も平気で登ってしまうので、脱走を防ぐ蓋つきの昆虫飼育ケースが必要です。
蓋には通気孔があるものを選びましょう。
カブトムシやクワガタ飼育で人気の「コバエシャッター」は、小さな虫の侵入やコバエの発生も防いでくれるのでおすすめの商品です。

100均ショップやホームセンターで500円前後で買える昆虫ケースでも、脱走防止の蓋がしっかりしていれば大丈夫です。
霧吹き
カタツムリは乾燥に弱いので、毎日1~2回程度、飼育ケースの内壁や餌となる葉っぱや野菜に霧吹きで水を吹きかけましょう。
霧吹きは、カタツムリに直接当たらないようにするのがポイントです。
カタツムリは肺呼吸しています。カタツムリは湿気を好むとはいえ、水浸しになってしまっては呼吸ができなくなってしまいます。
土
カタツムリが生息する自然環境により近づけてあげるよう、土を入れてあげる方が理想的かもしれません。
ただし、与える餌が好みとマッチすればよく食べ、そのぶん糞も多くなるので、土を入れると糞の掃除が大変になります。
手軽に観察を楽しむ程度なら、園芸用の水苔を湿らせたものを敷くのも趣があります。
土は植木鉢などに入れるとGood!
お手入れの面を考えると、小ぶりの植木鉢やガラス瓶に腐葉土や昆虫マットを入れて飼育ケースに置いてあげるスタイルもおすすめ。
カタツムリは土の中に産卵しますが、日常の生活環境と産卵場所を分けて用意してあげると、糞などお手入れが簡単です。
土の表面が乾かないよう、霧吹きで適度に湿らせてあげましょう。
木の枝(流木)
木の枝を入れると、カタツムリが上り下りする姿を観察できます。
また、隠れ家としても利用できます。
公園や林に落ちている木の枝を拾って使う場合は、虫やカビの有無を十分に確認します。
電子レンジで一度加熱処理すると、より安心です。
熱帯魚や爬虫類などペットショップで扱われている流木もよく乾燥処理され、1つ1つ趣のある形が素敵です。
餌皿
餌皿は、あくまでお手入れのしやすさを考えてのもの。
なるべく平らな小皿の方が安定します。形は丸でも四角でもOKです。
カタツムリの飼い方の注意点
カタツムリを飼う際には、以下の点に注意しましょう。
カタツムリは水が苦手!?霧吹きの量に注意!
カタツムリは湿った環境を好む一方で、水に浸かると肺呼吸ができず溺れてしまいます。
霧吹きで水を吹きかけるときは、その量に注意が必要です。
カタツムリの寄生虫に注意!
自然に生息しているカタツムリには、ほぼ全ての確率で寄生虫が存在しています。
とはいえ、大きく恐れることではありません。
基本的に自然に生息する生き物はみんな一緒です。
夏に子供たちが戯れるザリガニやカエル、草むらのバッタでさえ寄生虫は存在します。
カタツムリを触った後は、必ず石鹸でしっかり手を洗いましょう。
餌は少し大きめの方がいい
カタツムリは餌を小さくちぎって食べるのではなく、葉っぱや野菜など餌となる食べ物の上を移動しながら、歯舌(しぜつ)と呼ばれるヤスリのような歯で削りとるように食べていきます。
小さい餌を食べるのは苦手、餌は少し大きめの方が食べやすいようです。
スポンサーリンク
カタツムリの寿命は?
カタツムリの寿命は種類によって異なりますが、オナジマイマイなど多くみられるカタツムリの寿命は一般的に2~3年ほどです。
カタツムリの寿命は殻の大きさに比例するといわれ、殻の大きい種類ほど長生きします。
カタツムリは冬眠する?
カタツムリは冬眠します。
気温が下がり始める秋になると、餌をたくさん食べて体に栄養を貯え、石の下や葉っぱの裏など、外敵など危険の及ばない安全な場所に潜り込んで冬眠します。
冬眠中は殻の入り口に粘膜を張り、殻の中の乾燥を防ぎじっとしています。
カタツムリが冬眠中の注意点
飼育ケースの中でカタツムリが冬眠中も、ときどきは霧吹きしながら湿気を補いましょう。
寒さを凌ぐためと、暖房が効くリビングなどに置くのはよくありません。
暖房が効いて室温が上がると冬眠から目覚め、暖房が切れると再び冬眠に入ることを何度も繰り返すことで体力を消耗してしまうなど、うまく冬眠期間を過ごせません。
まとめ
カタツムリは、葉物野菜の他、身近な野菜や果物、卵の殻、コンクリートなど様々なものを食べる雑食性の生き物です。
カタツムリの寿命は、小さな種類でも2~3年で、殻の大きさに比例して長くなります。
紹介した飼い方を参考に、カタツムリが快適に過ごせる環境を整えながら上手に飼育し、観察を楽しんでください。
また、カタツムリは、人間にとって直接的な害はありませんが、寄生虫を持っている可能性があるので、触った後は必ず石鹸で手を洗いましょう。
スポンサーリンク