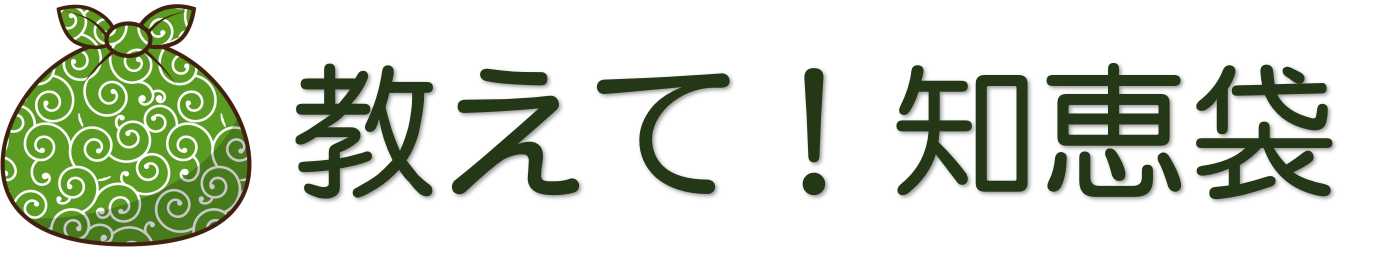スーパーでは鮮魚コーナーの端の方、仲良く並ぶ「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」。
塩味や食感を活かし、ご飯にのせて食べたり、サラダやパスタにトッピングしたりと、工夫次第で色々楽しめる食材である点はどちらも同じです。
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」、名前に違いはあれど見た目はほとんど同じで、使われる魚も似たような感じですよね。
色の感じや乾いた感じに違いがあると思いますが、具体的にはどんな違いがあるのでしょう。
今回は、「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」の作り方の違いや栄養素の違い、似たモノ同士で互いに代用できるのかなど、探っていきましょう。
スポンサーリンク
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」の違いは?!
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」、基本的にはどちらもカタクチイワシの稚魚を用いて作られていますが、季節によってはマルイワシやウルメイワシなど、小ぶりのイワシの稚魚を用いて作られることもあります。
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」をパックや量り売りで購入すると、どちらにも時折、小さなタコやイカのようなモノや他の魚の稚魚が混じっていることがありますよね。
あれを見つけると、小さな幸せを感じませんか?。なんだかラッキー!って感じてしまいます。
巷では、ちりめんモンスターとも呼ばれているようです。
『ちりめんモンスター🦑🐙』
いか🦑、たこ🐙、太刀魚┅
楽しく 朝ごはん~🍚🎶さぁ 💦
今日もファイトですっ🚩🚩#淡路産ちりめん#明石 #魚の棚 #座古海産 pic.twitter.com/oyzEcagigr— 明石魚の棚 座古海産 (@zakokaisan) February 4, 2021
使われる魚の種類に違いがないとなると、「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」の違いとは?。
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」の作り方の違い!
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」、よくよく比べれば見た目が少し違います。
乾いた感じで少し茶色い感じなのが「ちりめんじゃこ」で、白くしっとりふわっとした感じがするのが「しらす干し」。
その違いは、作り方の違いから生まれます。
干し方で呼び方が変わる!?
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」どちらもカタクチイワシの稚魚を主な材料に使い作られていますが、そもそも「しらす」とは漁獲されたイワシの稚魚を指す総称で、その後の作り方・加工方法によって異なる乾燥度(水分率)で呼び方・名前に違いが生まれます。
釜揚げしらす

漁獲されたイワシの稚魚「しらす」は、塩水で釜揚げしたあとの乾燥度(水分率)の違いで呼び方・名前が変わります。
釜揚げしらすとは、漁獲されたイワシの稚魚「しらす」をそのまま釜揚げして冷やしただけの、水分率が80%~90%と高い状態のモノです。
しらす干し

しらす干しとは、釜揚げしらすを機械や天日干しで水分率を65%~70%程度まで乾燥させたものです。
ちりめんじゃこ

ちりめんじゃことは、しらす干しをさらに、水分率40%~60%まで乾燥させたものです。
ちなみに「ちりめんじゃこ」という呼び名の由来は、しらすを天日干しする際に平らに広げられ乾燥していく姿を、「縮緬(ちりめん」の生地に見立てたものとされています。
乾燥度が高い(水分率が低い)ちりめんじゃこのメリットは、日持ちが長く「旨味成分」が凝縮されること。
逆に、しらす干し・釜揚げしらすと乾燥度が低く(水分率が高く)などほど、柔らかでふわっとした食感を楽しめる反面、日持ちは短くなってしまいます。
スポンサーリンク
「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」の栄養素とは?!
青魚を代表するイワシの稚魚を釜揚げした後、乾燥させて作られる「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」の魅力は、小さいとはいえ頭や骨も気にせず魚1匹1匹を丸ごと食べられること。
青魚といえば「DHA」や「EPA」などカラダにいい栄養素が豊富に含まれる食品として有名ですが、イワシの稚魚から作られる「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」からも同じように摂ることができます。
カルシウム
イワシの稚魚から作られる「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」は、小さくてもカルシウムはしっかり含まれています。
たとえば「しらす干し」を小皿1杯(100g程度)を食べると、約500㎎ものカルシウムを摂ることができます。
20代~40代の女性は1日に650㎎のカルシウムが必要とされますが、しらす干し小皿1杯でそのほとんどをカバーできてしまいます。
また、カルシウムを効果的に吸収するには「ビタミンD」の働きが重要とされますが、ありがたいことに「ちりめんじゃこ」や「しらす」にはビタミンDも含まれています。
骨の成長に欠かせない栄養素、カルシウム+ビタミンDを含む「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」は、成長期のお子様や授乳期のママさんにもおすすめの食材です。
DHAやEPAが豊富!
イワシの稚魚から作られる「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」ですから、当然ながら青魚に豊富に含まれるDHAやEPAと呼ばれる栄養素も豊富に含まれています。
DHA(ドコサヘキサエン酸)
血液の流れをサラサラにしてくれることに加え、脳や神経系の働きを高めてくれる効果が期待される成分です。
EPA(エイコサペンタエン酸)
DHAと同様に血液の流れをサラサラにしてくれることと共に、コレステロールを抑える働きが期待されます。
DHAやEPAは、マグロやサンマ、イワシなど青魚の頭の部分や目の後ろの脂身、皮などに多く含まれています。「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」なら、頭や骨も気にせず丸ごと食べられますね。
「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」の栄養素を効率的に吸収する食べ方!
「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」は、ご飯にのせてチョッとお醤油を掛けて食べたり、釜揚げの塩味はサラダやパスタのトッピングにも相性抜群です。
いつもの冷奴の薬味に加えて、「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」をトッピングしても美味しい。
「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」には、先に紹介したようにカルシウム・ビタミンD・DHA・EPAなどが豊富に含まれていますが、そこへ「お酢」やレモンなどの柑橘系の果物の果汁を加えて食べることで、クエン酸とカルシウムが結びつき、カルシウムの吸収効率が高まるとされています。
たとえば冷奴にちりめんじゃこをトッピングする場合、お醤油ではなく酸味を効かせてポン酢を一掛けしてみてはいかがでしょうか。
カルシウムの吸収率を向上させる、効果的な食べ方です。
スポンサーリンク
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」は代用できる?!
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」は、元々おなじイワシの稚魚から作られたもので、乾燥度(水分率)に違いがあるだけ。
代用できるのか?ではなく、逆にあえて代用することで、互いにいつもと違う食感や味わいを楽しめる間柄なのではないでしょうか。
ここでは、家庭でできる「しらす干しをちりめんじゃこへ変身させる方法」を紹介したいと思います。
しらす干しをちりめんじゃこに変身させる方法!

しらす干しをパックで買ってきても、なかなか食べきれないという方へ。
しらす干しは、乾燥度が低く(水分率が高い)あまり日持ちしないので、あえて「自家製ちりめんじゃこ」に変身させてしまうのも1つです。
味変ならぬ、食感を変えて楽しむことができます。
材料
しらす干し:100g
ごま油 :大さじ3
作り方
1.フライパンにごま油を入れ中火で熱します
2.しらす干しを入れたら、火力を弱火へ落とします
3.水分を飛ばしながら、根気よくカラカラになるまで炒めます
自家製ちりめんじゃこは、かなり簡単に作れると思います。ごま油が効いて香ばしく、食欲マシマシの一品に変身です。
まとめ
スーパーの鮮魚コーナーの一角で、仲良く並ぶ「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」。
似たもの同士だとは思っていましたが、使われる魚も同じで、カタクチイワシを基本にマルイワシやウルメイワシなど小ぶりのイワシの稚魚でした。
「ちりめんじゃこ」と「しらす干し」の違いは、漁獲後に塩水で釜揚げしたあとの干し方。
乾燥度が高い(水分率が低い)ちりめんじゃこメリットは、日持ちが長く「旨味成分」が凝縮されること。
逆に、しらす干し・釜揚げしらすと乾燥度が低く(水分率が高く)などほど、柔らかでふわっとした食感を楽しめる反面、日持ちは短くなってしまうのです。
どちらも、さすが青魚を代表するイワシの稚魚なだけあって、カルシウムやDHA、EPAなどカラダにいい栄養素がたっぷり含まれています!。
特に調理をせずとも、頭も骨も気にすることなくパクパクいけちゃうのがいい点ですね!。
もしも、しらし干しが残ってしまうときは、ぜひ今回紹介した簡単「自家製ちりめんじゃこ」への変身をチャレンジしてみてください。
スポンサーリンク